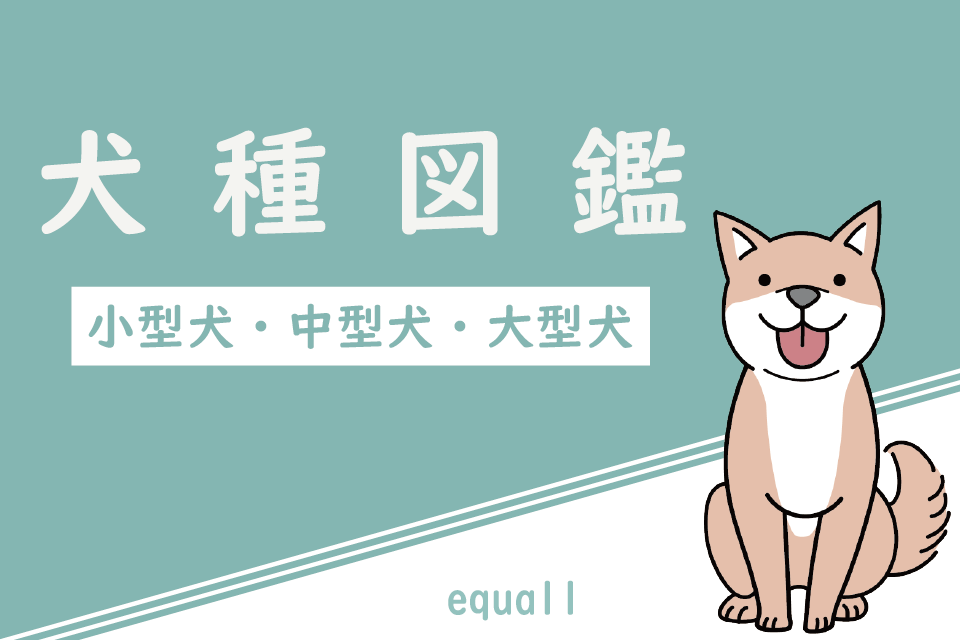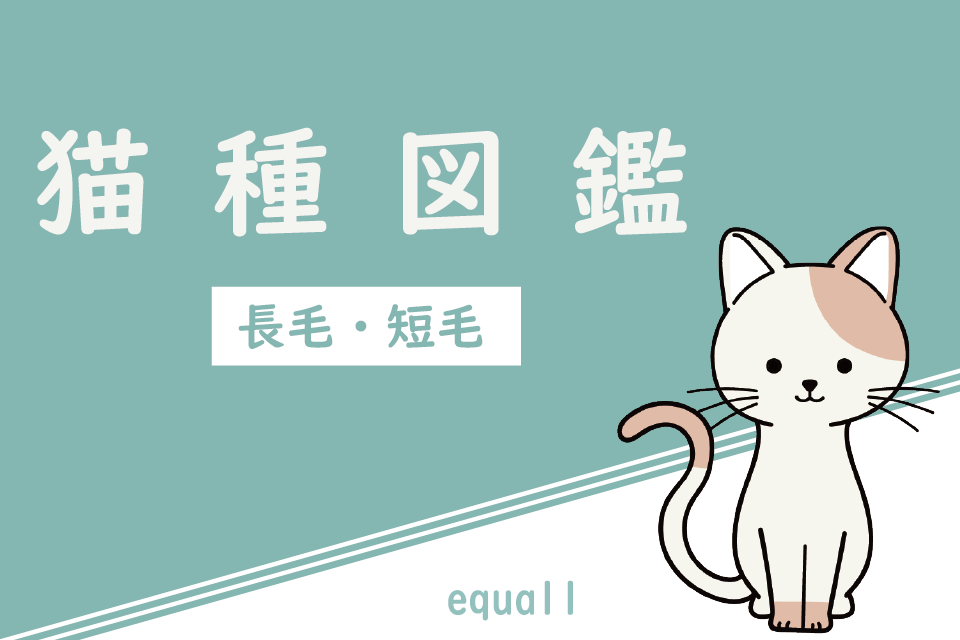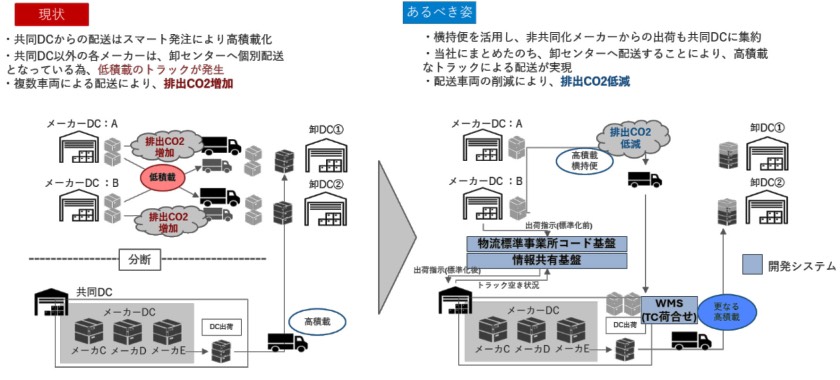近年、猫ブームの到来とともに「保護猫」という言葉をメディアで耳にする機会が増えました。しかし、一般市民の間でその実態は正しく理解されているのでしょうか?
今回は、保護猫をめぐる認知の現状、譲渡におけるハードル、そして今後の普及へのヒントを読み解きます。
目次
変化する数値と背景
まず、日本の動物愛護行政の変化について触れています。2010年代に入り、全国的に返還・譲渡率が上昇し、2020年には殺処分率と数値が逆転しました。調査対象地である岩手県においても、2017年には返還・譲渡率が殺処分率を上回っており、特に盛岡市では殺処分ゼロを継続するなど、官民連携による取り組みが進んでいます。
しかしその一方で、多頭飼育崩壊や安易な飼育放棄といった問題は後を絶ちません。この背景には、市民の意識や知識の格差が存在すると筆者らは指摘しています。
経験者と未経験者のギャップ
本研究の核となるのは、2021年に盛岡市周辺で行われたアンケート調査(有効回答708名)の結果分析です。ここで明らかになったのは、「保護猫」に対するイメージの大きな隔たりでした。
情報源による理解度の差
- 高認知層(よく知っている層):SNSや愛護団体のHPなどから能動的に情報を得ており、保護猫の実態を正しく理解しています。
- 低認知層(名前を聞いたことがある程度):テレビやラジオなど受動的なメディアからの断片的な情報が中心です。
ネガティブな先入観
保護猫や譲渡について詳しく知らない層(飼育経験なし・未検討層など)ほど、保護猫に対して以下のようなネガティブなイメージを持つ傾向が強いことが判明しました。
- 「人に慣れていない」
- 「衛生的ではない」
- 「しつけがされていない」
筆者らは、これらが報道などで目にする「保護直後の過酷な状態」の印象に引きずられた誤解であり、実際はシェルターでのケアや人馴れ訓練を経て譲渡される実態が伝わっていないことを指摘しています。
ペットショップ購入と保護猫譲渡
猫を入手する際の動機や心理においても、興味深い対比が報告されています。
「一目惚れ」のリスク
ペットショップでの購入者(予定者含む)が飼育理由として「ショップで一目惚れしたから」を挙げる割合は約2割に上ります。筆者らは、この「衝動買い」に近い行動が、飼育後の安易な放棄につながるリスクを懸念しています。
社会貢献としての譲渡
一方で、保護猫の譲渡を受けた人は、「社会貢献したいと思ったから」という理由が多く挙げられました。また、入手時の経済的負担(生体価格)が少ないことも、譲渡を検討する層にとってはメリットの一つとなっています。
譲渡を阻む「厳しすぎる条件」の壁
「保護猫を引き取りたかったが、断念した」という層が存在します。その最大の理由は「条件が厳しい」ことでした。アンケートでは、引き取りを断られた理由として以下が挙げられています。
- 「職種や生活習慣が飼育に向いていない(長時間労働など)」
- 「現在、多頭飼育である」
- 「自分や家族が高齢のため」
筆者らは、高齢化や単身世帯が増加する現代社会において、一律に厳しい条件を課すことは譲渡の機会損失につながると指摘します。例えば、高齢者には「永年預かり制度」を活用したり、飼い主にもしものことがあった場合の信託制度を整備したりするなど、条件の緩和と柔軟な仕組みづくりが提言されています。
「保護猫カフェ」という入り口の可能性
最後に、保護猫活動への市民の参加状況についてです。行政主導の「地域猫活動」などは認知度が低いのに対し、民間運営の「保護猫カフェ(例:もりねこ)」の認知度は非常に高い(特に岩手県内ウェブ回答者で8〜9割)という結果が出ました。
- 気軽さ:譲渡会のような「引き取らねばならない」というプレッシャーがなく、レジャー感覚で訪問できる。
- マッチングの質:何度も通って猫の性格を確認できるため、ミスマッチが防げる。
筆者らは、こうした「保護猫カフェ」が、関心の薄い層への普及啓発の拠点として、また行政施設(愛護センター)の代替機能として重要な役割を果たしていると評価しています。
これからの保護猫活動に向けて
本論文は、保護猫の譲渡をさらに普及させるために以下の3点が重要であると結論づけています。
- 正しい情報の発信:「汚い・慣れない」という誤解を解き、ケアされた保護猫の魅力を伝える広報戦略。
- 譲渡条件の見直し:高齢者や単身者でも飼育が可能になるような、サポート体制を含めた条件緩和。
- 接点の創出:保護猫カフェのような、市民が気軽に立ち寄れる「開かれた場」の活用。
「かわいそうだから助ける」だけでなく、「パートナーとして迎える」選択肢として保護猫が定着するためには、社会全体の意識変容と制度のアップデートが必要不可欠と言えるでしょう。
参考文献:保護猫の飼育・認知状況と譲渡普及―アンケート結果を中心とした考察一
執筆:equallLIFE編集部